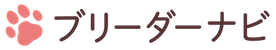バセットハウンドがかかりやすい病気、平均寿命は?
バセットハウンドは遺伝性疾患の種類が比較的多く、遺伝病以外にも、皮膚疾患や眼病にも気を付けてあげましょう。また、胴長短足という特徴的な体型ゆえに椎間板ヘルニアにも注意が必要な犬種です。
そんな、様々な傷病になりやすいバセットハウンドの寿命は10~12年程度といわれています。この寿命を短くするか長くするかは飼い主次第です。愛犬と一緒にすごす時間を長くするためには、運動や食事を管理して、何よりも健康に留意することが欠かせません。
では、バセットハウンドを飼う上で、特に注意しておきたい傷病を見ていきましょう。
たるんだ皮膚は病気になりやすいので注意
外耳炎
外耳炎は、外耳という耳の穴から鼓膜までの耳道という部分に炎症が起こる病気です。
バセットハウンドに限らず多くの犬種に見られる病気で、治療が遅れると慢性化してしまうため、早期の発見・治療が重要になります。再発の可能性が高く、体質によっては慢性化してしまう病気です。
<症状>
炎症により痒みや痛みが生じるため、首を振ったり傾けたり、後肢で耳付近をしきりに引っかくようになります。耳から悪臭がするようになり、重度になると腫れて耳の穴が塞がってしまいます。
<原因>
主な原因は、耳道に繁殖した細菌・真菌などの菌や、耳ダニなどの寄生虫、アレルギーです。バセットハウンドの特徴である長い垂れ耳は、通気性が悪いので湿気により原因となる菌が繁殖しやすい環境といえます。
<治療>
治療法は原因によって異なりますが、一般的に耳道の汚れを取り除き、炎症を抑えるための投薬治療が行われます。薬は点耳薬のほか、内服薬を用いることもあり、耳ダニが原因の場合は駆虫薬を使用することも。異物や腫瘍が原因ならそれらを取り除き、アレルギーの場合は並行してそちらの治療も行います。
<予防>
外耳炎を予防するには、耳を清潔に保つことが有効です。その上で、日頃からまめに耳をチェックして、異常があったら病院に連れて行くようにしましょう。過度な耳掃除やシャンプー液の耳への流入などが原因となる場合もあるので、この点には注意してください。
膿皮症
常在菌であるブドウ球菌が異常繁殖したことによって起こる、皮膚の化膿性病変が膿皮症です。犬の皮膚は人に比べ薄く性質も異なるので、健康であっても膿皮症が発症しやすくなっています。
症状が表皮内のみに現れる「表在性膿皮症」と、真皮に生じる「深在性膿皮症」という、2種類があります。
<症状>
膿皮症が発症するのは、特に脇や顔、内股、指間が多く、患部を舐めたり引っかいたりすると悪化してしまいます。湿疹や赤み、かゆみ、脱毛、フケなどの皮膚病変が現れ、重症になると膿瘍、発熱、痛みが出ます。
<原因>
膿皮症は皮膚のバリア機能の破壊や免疫力の低下などが原因で、ブドウ球菌が異常繁殖することで発症します。犬の皮膚は人間とは違い弱アルカリ性なので、この点も原因となっていることが多いようです。また、外傷や誤ったスキンケアにより肌を傷つけてしまうことで、膿皮症になることもあります。
特に、湿度が高い夏に発症が多いようです。
<治療>
基本的に、抗生物質の投与で治療していきます。表在性のものであれば、3週間ほどしっかり服用すれば治まっていきますが、深在性だと1~3ヶ月かかってしまうことも。症状によっては、内服薬と併用してシャンプー療法が行わる場合もあります。
基礎疾患がある場合は、原因となっている疾患の治療を行います。
<予防>
膿皮症の予防には、皮膚・被毛の手入れとシャンプーにより、皮膚の環境を清潔に保つことが大切です。ただし、過度にやってしまうと、逆に悪い影響を与えることになります。バセットハウンドの場合、シャンプーは月1回程度で十分です。
また、高温多湿の環境は皮膚の常在菌を繁殖させることになるので、温度・湿度を適切に管理するようにしましょう。
脂漏性皮膚炎
漏性皮膚炎は、完治しにくい慢性の皮膚病で、皮脂腺から過剰に脂が出たり、皮膚の角質化が極端に進んだりしてしまう病気です。
<症状>
激しい痒みや体からの悪臭、皮膚のベタつき、フケ、脱毛、発疹といった症状が現れます。
特に、趾間、会陰、顔面、腋窩(脇の下)、頚背部、腹部、皮膚のしわの間といった箇所の症状は重度になりやすい傾向があります。
<原因>
先天的な遺伝による場合もありますが、様々な要因が重なることで発症する場合もあります。また、ほかの皮膚炎が慢性化し起こることもあり、原因の特定は困難です。
考えられる原因は、ホルモンの分泌異常、食事中の脂肪のバランス、ビタミンAや亜鉛の不足、ダニやノミなど寄生虫や細菌感染、アレルギーなどになります。
<治療>
症状を抑えるために専用のシャンプーで薬浴し、かゆみ止めの飲み薬や塗り薬で治療を行います。また、脂漏症や合併症にあう、栄養バランスの取れた食事内容にします。
治療が遅れると慢性化してしまい、その文治療が長引くため、漏性皮膚炎は早期発見・治療が重要です。
治療のためにも予防のためにも「患部を清潔に保つ」「シャンプー後は被毛をしっかり乾かす」などを心掛けてください。
<予防>
治療法と共通することですが、一番の予防法は何よりも清潔を保つことです。また、食事内容も大切で、偏りのない栄養バランスの整った食事を心掛けるようにしましょう。
使用するシャンプーは脂漏症に合った物を選び、シャンプー後は丁寧に被毛を乾かし、濡れたままにしないようにしてください。
真菌症
真菌症は、胞子状の真菌に感染することで発症する病気で、円形状に脱毛する「リングワーム」が見られるようになり、進行すると全身に広がります。人畜共通感染症(ズーノーシス)であり、感染したワンちゃんと接触すると人間にも感染する危険性があるので注意が必要です。
成犬よりも子犬への感染率が高く、特に換毛期や被毛が活発に発育する時期に感染しやすい傾向があるようです。
<症状>
症状は全身に及ぶものの、特に顔や四肢への発症が多く見られます。
フケを伴うことが多く、初期症状に痒みはありませんが、症状が進行し細菌の二次感染が起こると強い痒みが出てきます。
感染から発症までの期間には個体差があり、体質の問題や飼育環境などの違いから期間にズレが生じます。
<原因>
皮膚や被毛に真菌が感染することで起こる病気で免疫力が低い子犬や抵抗力が落ちているワンちゃんに発症しやすい病気です。
真菌とは、カビに似た胞子状の常在菌で、目の周辺や耳、顔、口、脇の下といった、柔らかい場所に現れます。
<治療>
治療は、外用薬と内用薬の抗真菌薬を投与することで行われます。
被毛に感染した場合は患部の毛を刈ったり、抗真菌薬のシャンプーを使用した薬浴治療を行ったりすることもあります。
多くの場合、治療から症状の改善まで1ヶ月以上の期間を要します。
<予防>
真菌症を発症する最多の原因が、「真菌症に感染している動物からの感染」なので、最も有効な予防方法は、「感染している動物との接触を避ける」ことです。ただし、直接の接触がなくても、感染者が触れた物に触れるなどの間接的な接触でも感染してしまうので、完全に接触を避けるのは難しいといえるでしょう。また、感染者の抜け毛やフケから感染することもあることもあるので、極力清潔な環境で生活するようにしてください。
このほか「濡れたら丁寧に乾燥させる」「不調時にほかの動物との接触は避ける」などを心掛ければ、感染のリスクを減らすことができるでしょう。
胴長短足な体型的にかかりやすい病気
椎間板ヘルニア
バセットハウンドのように、胴長短足の犬種が患いやすい様々な神経症状を引き起こす病気です。椎間板が変性し、繊維輪に包まれた髄核という内容物が脊髄を圧迫することで痛みが生じるほか、四肢に麻痺が起きたり歩行が困難になったりします。
<症状>
軽度であれば、「動くことを嫌がる」程度で、明確な症状はありませんが、重篤化すると、四肢の麻痺により排泄のコントロールができなくなったり、立ち上がれなくなったりします。歩き方がおかしいようなら、この病気を疑うといいかもしれません。
ただし、椎間板が突出した場所によって接触した神経部位が異なるため、現れる症状も異なります。
<原因>
椎間板ヘルニアの原因の1つは、「加齢」です。高齢になると椎間板が脆く変質しやすくなり、ヘルニアが起こってしまいます。
もう1つは「遺伝」が原因です。先天的に「軟骨異栄養症」の遺伝子を持っているワンちゃんは、本来柔らかいゼリー状の髄核が硬くなりやすく、ヘルニアになってしまう確率が高くなります。
このほか、過激な運動をしたり脊髄に強い外力が加わったりすることでも、椎間板の変性が生じてしまいます。
<治療>
治療法は大きく分けて「内科的治療」と「外科的治療」の2通り。
症状が比較的軽ければ、投薬による内科的治療で改善を図ります。数週間の安静と鎮痛剤で回復を促します。場合によっては、ステロイドなどの消炎剤を用いたり、レーザー治療を行ったりすることもあります。
こういった治療では改善が見込めない、麻痺などの重篤な症状が確認できる場合、手術による外科的治療で対応することになります。手術により突出した椎間板を摘出し、術後はプールでの歩行や筋トレなどのリハビリを行うことで、回復を試みます。
<予防>
椎間板ヘルニアのリスクを最も上げるのは肥満です。遺伝的な原因の場合、完全に防ぐことはできませんが、適切な運動と食事管理で肥満を予防すれば、発症率を下げることができるでしょう。
また、滑りやすいフローリングにカーペットを敷いたり、高いところからの飛び降りをさせないようにしたり、日常生活で注意しておいてください。
胃捻転
胃捻転は、特に大型犬や超大型犬が多く発症する病気で、字のごとく胃が捻じれる病気です。症状が突如現れ進行も急激で、早急な治療が必要になります。最悪ショックから死に至ることもある危険な病気です。
<症状>
胃の中で大量のガスが発生することで胃拡張が生じ、それにより膨らんだ胃が回転、捻じれることで食堂が塞がれ更に拡張が進んでいきます。稀に拡張だけですみますが、ほとんどの場合は胃捻転が起こります。
一般的に、食後数時間以内に発症することがほとんどです。
まず立てなくなり大量のよだれを出しますが、この異変に気付いたら早急に動物病院に連れて行きましょう。その後、呼吸困難や脈拍の低下といったショック症状が現れ、数時間で死亡してしまいます。
<原因>
明確な原因は不明です。
食事や水分の摂取方法で早食いや大量摂取、食後すぐの激しい運動、ストレスなどで胃の異常運動が起き、胃内の液体やガスが増加することで胃拡張に伴い胃捻転が起こります。
例えば、多量のドライフードを食べた後に水を飲むことで、胃の内容物が膨張するとも考えられています。
<治療>
まずはチューブや注射針を使い胃内のガスを排出させ減圧し、ステロイドを投薬することでショック状態を治療します。落ち着いたら開腹し、捻じれた胃を元の位置に戻すとともに、再発を防ぐために胃を腹壁に固定する手術を行います。
<予防>
原因からも分かるように、早食いや大食いがリスクになるので、食事の習慣を見直すといいでしょう。また、食後すぐは運動しないように、大人しくさせてあげてください。
バセットハウンドのような大型犬は胃捻転のリスクが高い犬種なので、特に気を付けてあげてください。
最悪失明も!目の病気にも気を付けよう
チェリーアイ(第三眼瞼突出)
ワンちゃんの目には、上と下の瞼に加え「第三眼瞼(瞬膜)」という3つ目の瞼があります。チェリーアイとは、その第三眼瞼が炎症を起こし、裏にある第三眼瞼腺が飛び出してしまった状態です。赤く腫れ上がった第三眼瞼がまるでさくらんぼ(チェリー)のように見えることから、チェリーアイと呼ばれています。
<症状>
腫大した第三眼瞼腺が目を直接刺激するため目が充血し、不快感から目をこすったり頻繁に涙を流したりします。また、まぶしそうに目を細めまばたきの回数が増えるなど、目を開けていることが辛そうな様子が見られます。
チェリーアイは片目だけに発症することもあれば両目に症状が現れることもあり、細菌に感染すると、数倍の大きさに肥大することも。結膜炎や角膜炎を併発することもあるので、気付いたら早急に動物病院で診てもらってください。
<原因>
先天性な要因により発症することが多い病気です。
第三眼瞼腺は結合組織で眼窩骨膜と繋がっているのですが、この結合組織が先天的にない、もしくは弱い場合に発症しやすくなります。先天的な原因の場合、6ヶ月~1歳頃に発症することが多いようです。
また、目の炎症や外傷などが原因で、発症する場合もあります。
<治療>
治療は症状の重さによって、点眼薬や内服薬を使った内科的治療法と、第三眼瞼腺を切除する、または埋没するように引き戻す外科的治療法のどちらかを選択します。
以前は切除手術が主流だったようですが、涙液の30%を担う瞬膜腺がなくなるとドライアイになる危険性が高くなるので、現在はあまり行われていません。
術後は、エリザベスカラーをつけ目を保護したり、自宅で定期的な点眼薬の投与が必要だったりと完治までのケアも大切です。
<予防>
先天的な原因の場合予防は難しいので、早期発見・早期治療で対応することが重要です。
バセットハウンドはチェリーアイが発症しやすい犬種なので、こまめに目の状態をチェックして、少しでも異常があればすぐ動物病院で診てもらうようにしましょう。
外傷によるチェリーアイも、やはり早期発見・早期治療が重要です。
緑内障
眼球は内部に房水(眼房水)という液体で満たされています。これを眼圧(眼球内の圧力)といい、常に一定の房水が眼内を満たすことで、正常な形・サイズを保てているのです。
緑内障という病気は、眼内の房水の流れが何らかの原因によって阻害され、眼圧が高くなることで網膜や視神経が圧迫され、最終的には失明してしまいます。
<症状>
眼圧が上昇することで、目に激しい痛みを感じるようになります。
初期の症状は眼が少し赤くなる程度ですが、進行すると眼球が腫大するほか、目の充血、瞳孔の散大、角膜の白濁といった症状が現れます。また、目の痛みから目を細めたり閉じっぱなしにしたりするようになり、涙を多く流すようになることもあります。
分かりやすい「目が大きくなった」という状態になるとすでに失明してしまっており、こうなると現時点では「眼球摘出」か「シリコン義眼挿入術」という選択になってしまいます。
<原因>
先天的な原因におり自然発症する「原発性緑内障」と、ぶどう膜炎や水晶体脱臼などほかの病気によって発生する「続発性緑内障」の2つがあります。
バセットハウンドは先天的に房水が流れにくくなったり排出口が狭かったりする、「原発性緑内障」を発症しやすい犬種です。眼内を満たす房水が正常に排出されない一方、入ってくる房水の量は変化しないので、眼圧が上がりやすくなってしまいます。
<治療>
現状、緑内障は完治が見込めない病気で、ワンちゃんの状態や症状の程度、飼い主の意向によって内科的治療法と外科的治療法のどちらかを選ぶことになります。
内科的治療は、病気の進行を遅らせるための対症療法となり、内用薬や点眼薬、点滴により眼圧を下げることが目的になります。病状が進行しており、内科的治療だけでは対応できない場合は外科的治療となり、レーザーなどを用いて眼圧を下げる手術を行います。外科手術でも対応できない状態にまで進行していた場合――つまり完全に失明していた場合、眼球摘出術や義眼挿入などの手術を行うことになるでしょう。
緑内障の手術は専用の設備で行われ扱うための技術が必要になるため、かかりつけの動物病院が対応可能か事前に確認してください。
<予防>
先天的な原因であれ後天的な原因であれ、予防は難しい病気です。ただし、初期症状の段階で治療を行うことができれば、失明させずにすむかもしれません。とはいえ、眼球が腫大するといった分かりやすい症状が現れる頃には手遅れの可能性も…
日頃の行動や目の様子など、チェックを日常化することで、早めに異常に気付けるようにしましょう。
眼瞼外反症
眼瞼(まぶた)がめくれてしまう病気で、外側にめくれている状態を「眼瞼外反症」といいます。これによりまぶたの結膜が露出してしまい、角膜や結膜に刺激を受け炎症を起こしたり、細菌感染を起こしてしまったりする病気です。
正常に涙を排出できなくなるので、常に涙ぐんで見えます。
<症状>
眼瞼外反症の症状として、常に涙と目やにが眼にたまっているようになります。
目の痛みや痒みから、前足で顔をこするなど目を気にする動作をするようになり、角膜や結膜が露出することで結膜炎や角膜炎を発症しやすくなります。
<原因>
先天性・後天性2通りの原因があり、一般的に先天的な原因により発生することが多い病気です。
バセットハウンドをはじめ、皮膚がたるんでいる犬種がなりやすい傾向にあります。
後天的な原因としては、「老化により顔の筋肉量が衰える」「麻痺などによりたるみが起こる」などの影響で、眼瞼外反症を起こしてしまうこともあります。このほか、結膜炎や外傷の後遺症により発症すことが確認されています。
<治療>
涙膜異常や炎症といった、明確な症状が確認できない場合、治療を行わないことも少なくありません。一時的に結膜炎などの症状が出ているようであれば、点眼薬を使用しながら経過を観察します。
あまりに外反が酷い場合は、手術で患部を切り取り縫合し、まぶたの形状を矯正する場合もあります。原因や程度によって手術の方法は異なり、一度手術で治ったとしても、加齢で眼瞼外反症が再発する例もあるので、注意が必要です。
また、ほかの病気が原因で眼瞼外反症の症状が出ている場合は、まず原因となっている病気を優先的に治療してから眼瞼外反症の治療を行います。
<予防>
眼瞼外反症を予防する明確な方法はありません。しかし、眼瞼外反症は見た目でわかりやすい病気なので、比較的早い段階で見つけることができるでしょう。
瞼の状態に違和感を感じたら、症状が重くなる前に、できるだけ早めの通院をおすすめします。
バセットハウンド特有?血液の病気
バセットハウンド血小板障害
劣性遺伝によって発症する先天性の病気で、血小板の機能障害により怪我などで一度出血すると血が止まらなくなります。
<症状>
出血した時など、凝固することで傷口を塞ぐ役割を担う血小板ですが、遺伝的にこの機能が弱く出血しやすく止まりにくくなります。重症になると、鼻血や血便、血尿などが止まらなくなることもあります。
血液を失うということは死に直結するので、決定放置してはいけない病気です。
バセットハウンドを飼うのなら、万が一に備えて事前に検査しておく必要があるでしょう。
<原因>
バセットハウンドという犬種特有の病気で、劣性遺伝により発症します。
<治療>
遺伝性の病気なので、根本的な治療方法はありません。
出血してしまった場合、輸血により対応することが多いようです。
<予防>
遺伝性の病気なので予防はできませんが、余程症状が重くない限り、出血しないことが一番大切です。
まとめ
バセットハウンドは、他と比べても注意すべき病気が多い犬種です。中には命に関わるような病気や、バセットハウンドという犬種特有の病気もあり、長生きしてもらうためには、日常的にケガや病気に気を付けておく必要があるでしょう。
ブリーダーナビは、安心価格と取引保証で、顧客満足度98.9%!
掲載されているワンちゃんの頭数も本最大級の子犬販売サイトです。
バセットハウンドの子犬をお探しなら、優良ブリーダーが手掛けた子犬をたくさん掲載しているブリーダーナビを、ぜひ一度ご覧ください。
著者/ブリーダーナビ編集部